「ワインって太るの?寝る前に飲んでもいいの?」と気になる方は多いでしょう。知りたいのは、寝る前ににワインを飲むと体型にどんな影響があるのか、ワインを飲んだ後の歯磨きは避けるべきって本当か、という点です。さらに、寝る前に飲む白ワインとチーズの相性、おすすめの種類や適量、白赤ワインのダイエット効果といった話題も関心を集めています。
加えて、夜に選ぶべきワインのタイプ、ワインは太りやすいお酒なのかという素朴な疑問、ワインに痩せる効果があるのか、ワインとビールどっちが太るのかも比較し、不安を解消します。

- 日本ソムリエ協会認定の現役ソムリエ
- 現役バーテンダーでもあるお酒のプロ
- 家飲みでいかにワインをおいしく楽しむか探求中
- 夫婦そろってソムリエなので、記事情報の正確さには自信あり
本記事では、こうした疑問を初心者にもわかりやすく解説。公開されている客観的な情報を整理ながら紹介していきます。
- 寝る前にワインを飲むときの影響と上手な楽しみ方がわかる
- 寝る前に飲む白ワインや赤ワインの選び方が理解できる
- 適量の目安や飲み過ぎを防ぐための実践的な工夫が身につく
- ワインとビールのカロリーや太りやすさの違いを比較できる
ワインは太る?寝る前に飲むなら知りたいこと

- ワインは太りやすいお酒?をわかりやすく解説
- ワインを飲んだらすぐ歯磨きは危険って本当?
- 寝る前に飲む、白ワインを選ぶときのポイント
- 寝る前に飲む、赤ワインを選ぶときのポイント
- チーズと合わせて楽しむコツ
- 寝る前に飲むワインでおすすめの種類は?
- 量の目安と飲み過ぎ防止のポイント
ワインは太りやすいお酒?をわかりやすく解説
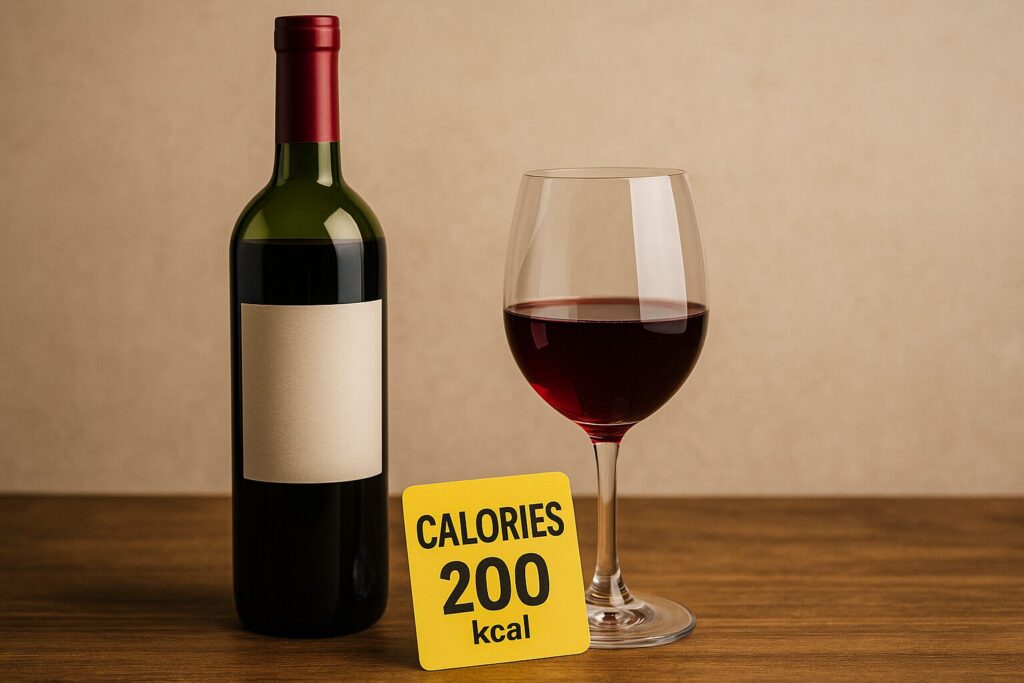
ワインが太りやすいかどうかは、アルコールと糖質の含有量で考えることができます。文部科学省の食品成分データベースによると、赤ワイン100mlあたりのエネルギーは約68kcal、白ワインは約75kcal、糖質はそれぞれ1.5g前後とされています(出典:日本食品標準成分表 八訂)。ビールは同量で約40kcalですが、飲む量が多くなりやすいため、総摂取カロリーは逆転する場合があります。
ワインは糖質量が比較的少ない一方で、アルコール度数が高い分エネルギーはやや高めです。量をコントロールすれば太りやすいお酒とは限らないとされます。ポイントは「どれくらいの頻度と量で飲むか」です。1回あたりグラス1杯程度なら、エネルギー摂取量は大きくなりにくいと考えられます。
| 飲料(100ml) | エネルギー目安 | 糖質目安 |
|---|---|---|
| 赤ワイン | 約68kcal | 約1.5g |
| 白ワイン | 約75kcal | 約2.0g |
| ビール | 約40kcal | 約3.1g |
※数値は代表値であり、銘柄やスタイルによって変動します。
ワインは飲むペースをゆっくりにすることで、結果的に摂取量が抑えられます。小ぶりのグラスや細めのステムを選ぶと、視覚的にも少量で満足しやすくなります。
ワインオープナーがなくてボトルを開けられない場合は、» ワイン オープナー 代用の最適解は?初心者必携ソムリエナイフ3選の記事で詳しく解説しています。
ワインを飲んだらすぐ歯磨きは危険って本当?

ワインを楽しんだ直後の口の中は、飲み物自体の酸と香味成分の影響で一時的に酸性になっている状態。歯の外側を覆うエナメル質は非常に硬い一方で、pHがおよそ5.5を下回る環境では脱灰(表面がやわらぐ現象)が進みやすいとされています。口腔内では唾液が酸を中和し、カルシウムやリン酸を供給して再石灰化(※)を助けるため、時間経過とともに状態は戻っていきます。
この仕組みから、「飲んですぐに強くこするブラッシングは避ける」というケアの考え方が一般的。対応としては、まず水で軽くすすぐ、酸が強いワインのあとであれば30〜60分ほど時間を置く、そのうえでやさしくブラッシングする、といった手順がおすすめです。歯ブラシは毛先が開いていない柔らかめ、ペーストは研磨成分が強すぎないタイプを選ぶなど、物理的な擦過を抑える配慮が推奨されています。
※再石灰化(さいせっかいか)…唾液中のミネラルが歯の表面に戻り、軟化したエナメル質を補強する自然な回復過程。食後・飲用後に時間を置く意義の説明でよく出てくる言葉です。
あわせて、就寝前というタイミング特有の注意点も挙げられます。睡眠中は唾液分泌が低下しやすく、口腔内を守る自浄作用が日中より弱まりやすいとされるため、寝る直前に酸性飲料を摂る場合は、すすぎ・時間調整・やさしいケアの三点を意識しておくことが推奨されています。
フロスなどの清掃補助具は、エナメル表面をこするブラッシングと比べると酸の影響を受けにくいとされ、「歯間清掃→時間を置いて全体のブラッシング」の順にする工夫することも大事なポイントです。
注意するポイント
最適なケアは口の状態(詰め物・知覚過敏・エナメルの厚み等)によって異なるため、定期検診などで歯科の先生にチェックしてもらいましょう。一般的な方法はあくまで目安であり、個別の診断やケアを促すものではありません。
歯科の一般的なセルフケア手順やタイミングについては、公的医療サービスの資料でも基礎的な考え方が紹介されています(出典:NHS How to keep your teeth clean)。
寝る前に飲む、白ワインを選ぶときのポイント

夜にグラス一杯のワインを楽しむなら、ラベルのアルコール度数(ABV)、甘辛の表記、ブドウ品種、産地、スタイル(スパークリング/スティル)を手掛かりに確認すると選びやすくなります。
たとえばABVはおおむね9〜14%の範囲で見かけることが多く、数字が低いほどボディ(重さ)の体感は軽くなりやすいです。甘辛は「Dry(辛口)/Off Dry(やや辛口)/Medium(やや甘口)/Sweet(甘口)」などの表現が使われ、寝る前の一杯なら、香りが立ちやすく口当たりが軽い辛口寄りを基点にワインを選びましょう。
温度も大切です。白は6〜10℃程度が一般的な目安として語られますが、冷やしすぎると香りが閉じやすく、温度が上がりすぎると酸が緩んで平板に感じられることがあります。家庭では冷蔵庫で十分に冷やし、注いでからグラス内で少しだけ温度が上がる過程を楽しむのが取り入れやすい方法です。グラスは小ぶりのチューリップ型を選ぶと、香りを逃がしにくく、飲み過ぎにくい分量で注ぎやすいという実務上の利点もあります。
・平日の夜に軽く…ABV 10〜12%、辛口寄り、柑橘や青りんごの香りが目印の品種(例:ソーヴィニヨン・ブラン、ピノ・グリージョ)
・香りをしっかり…ABV 12〜13.5%、熟した果実や白い花の香り、樽由来のバニラ感が少し(例:シャルドネの一部スタイル)
・泡で気分を変える…辛口スパークリング(Brut表示)。細かな泡は口中をリセットしやすく、一杯で満足感を得やすい
ラベルに見慣れない用語が並ぶと難しく感じがちですが、「ABV・甘辛・品種・泡か静かか」の四点に絞って眺めれば十分に直感的に選べます。加えて、寝る前は食事量が多くなりにくい時間帯でもあるため、香り主体で楽しめるスタイルを選ぶと満足度が高まりやすいです。
なお、香りの感じ方や飲み心地には個人差が大きいため、初心者はハーフボトルや小容量缶・瓶タイプを試してみるなど、「小さく試して好みを特定」するアプローチが現実的です。
| 見るポイント | 目安 | 期待できる印象 |
|---|---|---|
| ABV | 10〜12% | 軽快で飲み疲れしにくい |
| 甘辛表示 | Dry〜Off Dry | すっきり、食と合わせやすい |
| 品種 | SB/PG/Ch等 | 柑橘〜白花〜樽香まで幅広く選べる |
| スタイル | スパークリング | 泡の清涼感で一杯でも満足感 |
※表は一般的に語られる傾向の整理。銘柄・産地・ヴィンテージにより印象は変わります。
寝る前に飲む、赤ワインを選ぶときのポイント

寝る前に赤ワインを楽しむなら、渋味やボディの重さを意識して選ぶのがおすすめです。ピノ・ノワールやガメイなどのライトボディは口当たりがやわらかく、リラックスタイムに向いています。ミディアム〜フルボディの赤(カベルネ・ソーヴィニヨン、メルローなど)は味わいがしっかりしているため、少量でも満足感が得られ、飲みすぎ防止につながります。
温度は16〜18℃前後が目安とされ、香りを引き出すために少し高めの室温で楽しむと、味わいがより豊かになります。赤ワインはグラスの形状によっても香りの広がり方が変わるため、可能であれば赤ワイン用の大きめのグラスを用意すると良いでしょう。
| 品種 | ボディ | 渋味 | 香りの特徴 |
|---|---|---|---|
| ピノ・ノワール | ライト〜ミディアム | 穏やか | チェリーやラズベリーなど赤い果実の香り |
| メルロー | ミディアム | まろやか | プラムやチョコレートのような丸みのある香り |
| シラー(シラーズ) | フルボディ | しっかり | スパイスやブラックベリー、スモーキーな香り |
| カベルネ・ソーヴィニヨン | フルボディ | 力強い | カシスや杉、ハーブ系の複雑な香り |
| ガメイ | ライト | 非常に軽い | イチゴやキャンディのようなフレッシュな香り |
※ボディは軽いものほどさらっと飲みやすく、重いものは少量で満足感が高い傾向があります。
寝る前はアルコール度数が高すぎないタイプを選び、ゆっくり時間をかけて1杯を味わうと、翌朝もすっきりしやすいとされています。
チーズと合わせて楽しむコツ

夜の一杯にチーズを添えるなら、「味の強さをそろえる」という考え方が役立ちます。白ワインの軽快さに対しては、フレッシュタイプのチーズ(例:モッツァレラ、リコッタ)や、塩味が穏やかでミルキーなソフトタイプがなじみやすい傾向があります。
コクのある白や軽めの赤なら、セミハード〜ハード(例:ゴーダ、コンテ)が合いやすく、赤い果実の香りがあるライトボディの赤には、やや熟成の進んだチーズが合います。
チーズの塩分と脂肪は、口の中で味と香りの持続を伸ばします。辛口の白にフレッシュチーズを合わせると、ワインの酸が生乳の甘さを引き立て、「もう一口」の循環が生まれやすくなります。逆に塩や旨味が強いチーズを軽い白に合わせると、チーズが優勢になりやすいので、ワイン側を一段階ボディのあるタイプに引き上げる、もしくは少しだけ温度を上げて香りを開かせるなどの微調整が有効です。
ワインのペアリングについて詳しく知りたい方は、≫ ワインペアリングの完全ガイド|簡単にできるマッチングの楽しみ方も解説の記事でわかりやすく深堀りしています。
なぜ就寝前におすすめ?
チーズとワインの組み合わせは、少量でも満足感を与えやすく、夜のリラックスタイムにぴったりです。チーズのトリプトファンはセロトニンの材料となり、心身を落ち着ける効果が期待できます。アルコールは適量なら副交感神経を優位にし、体をリラックスモードに導いてくれます。就寝前に過度に食べず、味と香りを楽しみながらゆっくり口にすることで、翌朝に重さを残さず心地よく眠れる人も多いのです
迷ったときの組み合わせ早見
- 辛口の白 × フレッシュチーズ(ミルキーで塩控えめ)
- コクのある白 × セミハード(ナッツ様のコクで調和)
- ライトな赤 × セミハード〜やや熟成(果実味と旨味の均衡)
- 爽やかなロゼ × ハーブ入りチーズ(香りの相乗効果)
一度に多く食べない夜の時間帯は、少量を数種類用意すると満足度が上がります。塩気が強いチーズのときは、無塩ナッツや薄切りフルーツ、軽く焼いたバゲットを添えると口中が整い、次のひと口が新鮮になります。
チーズの温度も要点で、冷え過ぎは香りが閉じやすいため、室温で10〜15分程度置いてから出すと風味が立ちます。盛り付けは色のコントラスト(白いチーズ+緑のハーブ+赤い果物)を意識すると、視覚的満足感も高まり、「一杯で満ちる」夜の時間をつくりやすくなります。
| ワインの印象 | おすすめのチーズ | ひと言メモ |
|---|---|---|
| 軽快・柑橘・辛口白 | モッツァレラ/リコッタ | ミルキーさが酸を優しく受け止める |
| コクのある白 | ゴーダ(若め)/コンテ | ナッツ様のコクが厚みを補って調和 |
| ライトボディの赤 | セミハード〜やや熟成 | 赤果実と旨味の均衡が取りやすい |
| ロゼ(フレッシュ) | ハーブ入りチーズ | 香りを重ねて爽やかに |
※組み合わせは傾向の一例です。好み・銘柄によって印象は大きく変わります。
夜はつい手が伸びやすい時間帯です。チーズはカット量を先に決め、「皿にのった分で終わり」のルールを用意すると量のコントロールがしやすくなります。
寝る前に飲むワインでおすすめの種類は?

夜のリラックスタイムは、選ぶワインの「軽やかさ」と「香りの出方」で印象が大きく変わります。就寝前に向くといわれるのは、少量でも香りがよく立ち、重たさを感じにくいスタイルです。ここでは、初めての方でも迷わず選べるように、タイプ別の特徴・目安となるアルコール度数(ABV)・温度のヒント・一杯の目安量まで具体的に整理します。
軽やかな白:爽快で飲み疲れしにくい
ソーヴィニヨン・ブラン(柑橘やハーブの香り/ABV目安11.5〜13%)、ピノ・グリ(ピノ・グリージョ)(白桃や梨のふくよかさ/11.5〜13%)、アルバリーニョ(潮のニュアンスとライムのような酸/11.5〜12.5%)は、いずれも口当たりが軽く、香りの立ち上がりが早いのが特徴です。冷やしすぎず8〜12℃を目安にすれば、香りが閉じずに楽しめます。
アロマティックな白:華やかな香りで満足感を高める
ゲヴュルツトラミネール(ライチやローズ/12〜13.5%)やモスカート(マスカット)(フローラルでやさしい甘み/5〜7%の微発泡も多い)は、香りが主役。少量でも満足感が得られやすく、就寝前の一杯をゆっくり香りで味わいたい人に向いています。やや甘口でも、温度は10〜12℃に保つと香りがきれいに開きます。
フレッシュなロゼ:食後の“つなぎ”に万能
イチゴや赤い花の香りをもつ辛口ロゼは、白の軽快さと赤の果実味の中間的な立ち位置。ABVは11.5〜13%が中心で、8〜10℃に冷やすと輪郭がはっきりします。油分のあるおつまみ(オリーブ、スモークサーモン)とも合わせやすく、口中をすっきり整えます。
スパークリング:泡で口中リセット、糖度表示もチェック
微細な泡は口中をリフレッシュし、食後の余韻を整えます。ブリュット(辛口)を選ぶと後味が軽く、12%前後が一般的。ラベルの甘辛表示は次のとおりで、就寝前はブリュット〜エクストラ・ブリュットが選ばれやすい傾向です。
| 表示 | 残糖の目安(g/L) | 就寝前の相性 |
|---|---|---|
| Brut Nature | 0〜3 | 非常にドライで切れ味重視 |
| Extra Brut | 0〜6 | 香りを邪魔しない辛口 |
| Brut | 0〜12 | バランス良く最も選びやすい |
| Extra Dry / Sec など | 12〜32 | やや甘み、デザート寄りの余韻 |
※表示は国や生産者で幅があるため、実際の印象は銘柄により異なります。
軽めの赤:温度を少し下げて、さらりと
ピノ・ノワール(赤いベリーの香り/12.5〜13.5%)やガメイ(キャンディのようなフルーツ感/11.5〜13%)は、渋味(タンニン)が穏やかで就寝前にも取り入れやすいタイプ。12〜14℃に軽く温度を下げると、重さを感じにくくなります。大ぶりグラスで香りを広げ、量は少なめに。
酒精強化(ポート/シェリー):少量で満足、ゆっくり味わう
アルコール度数が高め(17〜20%)のポートやシェリーは、香りの複雑さが魅力。就寝前は30〜60mlの少量を目安に、常温寄りの温度で時間をかけて楽しむと満足感が得られます。香りが強いため、ナッツやハード系チーズをほんの少し添えるとバランスが取りやすくなります。
| スタイル | ABV目安 | 提供温度 | 一杯の目安 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|
| 軽やかな白(SB/PGなど) | 11.5〜13% | 8〜12℃ | 90〜125ml | 軽快で香りが立つ、初めてでも選びやすい |
| アロマティック白(GWT/モスカート) | 5〜13.5% | 10〜12℃ | 75〜120ml | 少量で満足感、甘さは銘柄で差 |
| 辛口ロゼ | 11.5〜13% | 8〜10℃ | 90〜125ml | 食後の口直しに万能、すっきり |
| スパークリング(Brut) | 11.5〜12.5% | 6〜8℃ | 90〜120ml | 泡でリセット、辛口表示を目安に |
| 軽めの赤(ピノ/ガメイ) | 11.5〜13.5% | 12〜14℃ | 90〜120ml | 渋味控えめ、温度を下げて軽やかに |
| 酒精強化(ポート/シェリー) | 17〜20% | 14〜18℃ | 30〜60ml | ごく少量で香りを楽しむスタイル |
実践のコツ:グラスに注ぐ上限ラインを決める/チェイサーの水を用意する/香りを確かめながらゆっくり飲む——この3つで満足度とメリハリが上がります。おつまみは軽め(フレッシュチーズ、ナッツ、白身魚のスモークなど)にすると、香りが主役のまま楽しめます。
注意:就寝前は節度ある量が前提とされています。適切な飲用の考え方は、公的ガイドラインで「節度ある適量の推進」として示されています。詳細は(出典:厚生労働省「健康日本21(第三次)」)をご確認ください。
量の目安と飲み過ぎ防止のポイント

ワインを寝る前に楽しむ際、量をコントロールすることが満足感と翌日の快適さを両立させます。量の把握には純アルコール量という指標が役立ちます。
計算式は「容量(ml)×アルコール度数(%)×0.8」で求められ、たとえば125ml・アルコール度数14%のワインは約14gの純アルコールを含むと計算されます。この数値を知ることで、健康日本21が目標とする「男性1日40g、女性1日20g未満」を意識した飲み方ができます。
具体的な対策として、グラスに注ぐ量を一定に決める、食事と一緒にゆっくり飲む、途中で炭酸水やノンアルコール飲料をはさむなどの方法があります。これにより自然とペースが落ち、飲み過ぎ防止になります。ワインクーラーやアイスペールを使って適温を保つのも、つい注ぎすぎることを防ぐ助けになります。
飲酒習慣がある人は、週に1〜2日の休肝日を設けることも推奨されます。休肝日を作ることで肝臓への負担を軽減できるとされています。
注意:量の目安はあくまで一般的な健康指標であり、体格や体調によって適切な量は変わります。飲酒に伴う体調不良が続く場合は専門家への相談が勧められます。
ワインで太るのを避ける|寝る前にワインをもっと楽しむために

- 白ワインのダイエット効果は本当?
- 寝る前の赤ワインとダイエット効果の関係
- ワインとビールはどっちが太る?比較で解説
白ワインのダイエット効果は本当?

白ワインに含まれるポリフェノールや有機酸は、抗酸化作用や代謝への影響が研究されていますが、ダイエット効果を裏付ける決定的な科学的証拠は限定的とされます。いくつかの基礎研究では、ブドウに含まれる成分が脂質代謝に影響を与える可能性が示唆されていますが、人間を対象とした臨床試験では結果が一貫していません。
つまり、白ワインをダイエット目的で積極的に飲むのではなく、適量を守りつつ食事と一緒に楽しむスタイルが現実的です。白ワインは爽やかな酸味と果実味が特徴で、低脂肪の料理や魚介類と合わせると満足感が高まりやすく、結果として過食を防ぐ効果が期待できる場合もあります。
白ワインのカロリーは100mlあたり約75kcalとされ、ビールやチューハイと比較すると糖質量は少なめです。とはいえアルコール自体にもカロリーがあるため、飲み過ぎればエネルギー過多につながります。
ダイエット効果を狙った飲用は推奨されません。公式サイトや公的機関も、飲酒はあくまで嗜好品として楽しむものであり、健康維持の手段として奨励されるものではないとしています。
寝る前の赤ワインとダイエット効果の関係

赤ワインにはポリフェノールの一種であるレスベラトロールやタンニンが含まれ、抗酸化作用や脂質代謝との関連が研究で示唆されることがあります。ただし、人における体重減少効果は科学的根拠が十分ではないとされており、公的な健康情報でもアルコール摂取と体重変化には個人差が大きく、明確な因果関係は限定的と説明されています(参照:Harvard Health Publishing)。
寝る前に赤ワインを楽しむなら、ライトボディのピノ・ノワールやガメイなどは口当たりがやわらかく、夜のリラックスタイムに向いています。ミディアム〜フルボディのカベルネ・ソーヴィニヨンやシラーは香りと渋味がしっかりしており、少量でも満足感が得られるため、飲みすぎを防ぎたいときに適しています。
レスベラトロールはブドウの皮に多く含まれますが、ワイン1杯あたりの含有量は研究で使われる量より少ないとされています。健康効果を期待するよりも、風味や食事との相性を楽しむ目的で飲むのが現実的です。
赤ワインを「痩せる目的」で大量に飲むことは推奨されません。カロリーオーバーや睡眠の質低下につながる可能性があるため、適量を守り、嗜好品として楽しむことが大切です。
ポイントとして温度は16〜18℃に調整し、香りを確かめながらゆっくり飲むと満足感が高まり、飲みすぎ防止にもつながります。
ワインとビールはどっちが太る?比較で解説

「ワインとビールどっちが太る?」という疑問は多くの人が抱きます。カロリーだけを見れば、ビールは100mlあたり約40kcal、ワインは赤で約68kcal、白で約75kcalとされます。
しかし実際に飲む量を考えると、ビールはジョッキ1杯(約500ml)、ワインはグラス1杯(約120〜150ml)で提供されることが多いため、総摂取カロリーは飲み方次第で逆転する可能性があります。
さらに、ビールは炭酸で喉ごしがよく、つい飲み進めてしまう傾向がある一方、ワインは少量ずつ味わうため、結果的に摂取量が少なくなるケースもあります。太るかどうかは飲む量と頻度の問題であり、飲料そのもののカロリーだけで一概に判断することはできません。
| 飲料 | 一般的な提供量 | 純アルコール量(目安) | 総カロリー(目安) |
|---|---|---|---|
| 赤ワイン | グラス125ml | 約14g | 約85kcal |
| 白ワイン | グラス125ml | 約14g | 約93kcal |
| ビール | ジョッキ500ml | 約20g | 約200kcal |
※数値は文部科学省食品成分データベースを基にした代表値です(出典:食品成分データベース)。
比較すると、ビールは1杯あたりのカロリーが多くなりがちです。寝る前に飲む場合は、量をあらかじめ決めておくことが重要です。小ぶりのグラスを使う、食事と合わせて時間をかけるといった工夫で、過剰な摂取を防げます。
ワインは一口ごとに香りを確かめながら飲むため、結果的に飲酒ペースが落ち、総摂取量が抑えられやすいとされます。
まとめ:ワインで太るのを避ける|寝る前の上手な楽しみ方
- ワイン 太る 寝る前の疑問は客観的情報で整理して安心
- 寝る前は軽めのスタイルを選び少量をゆっくり楽しむ
- 酸味の強い飲み物の後は水ですすぎ歯磨きは時間を置く
- 白ワインは辛口寄りを選ぶと食事と合わせやすい
- チーズはワインと味の強さをそろえてバランスを取る
- おすすめは香りの良い白やロゼでリラックス時間に適す
- グラスの注ぎ量を決めて飲み過ぎを防ぐ習慣を作る
- 純アルコール量の計算式を覚え適量を意識して選ぶ
- 健康日本21の目安を参考に日々の飲酒量を見直す
- 基礎研究の結果は人での効果が限定的と理解しておく
- 渋味が苦手ならライトボディ赤ワインから試すと良い
- ワインとビールは容量とカロリーを比較して選択する
- 夜は食事との相性を意識し香りを楽しむペースで飲む
- ワインは視覚と香りで満足感を高める工夫をすると良い
- 参照リンクで最新の公的情報を確認して習慣を更新する

